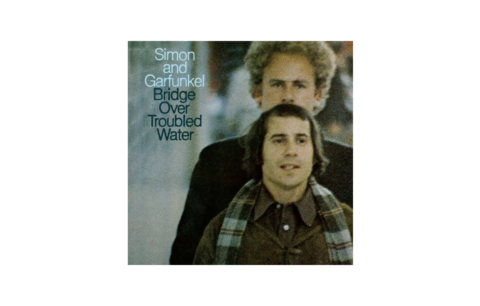南野 尚紀
The Modern Jazz Quartetの名前は、『ダンス・ダンス・ダンス』の冒頭で、「月世界の女性と結婚しなさい」という女性と、主人公の僕がベッドに入る少し前のテーブルで話しているシーンで出てくる。
村上春樹は相当、モダンジャズ・カルテット好きみたいで、『ポートレート・イン・ジャズ』でも、彼らをほめてた。
今となっては、あまり名前も出てこなくなったピチカートファイブの小西康陽も、モダンジャズ・カルテットは好きだったみたいだけど、僕もこのバンドは大好きだ。
60年代から20年間にかけて、長く人気を集めたジャズバンドで、静かな音遣い、清潔感のあるスーツに身を包んだ佇まい、スマートな音楽スタイルが当時のジャズマニアを唸らせたそうだ。
モダンジャズ・カルテットの心地よさは、インテリジェンスとフィーリングの混ざり具合にあって、そのインテリジェンスも一歩引いたような批評性にある。
ミルト・ジャズクソンのヴィブラフォン(鉄琴)は、眠くなってしまうような甘さもあるんだけど、謎を解き明かすシャーロック・ホームズの推理のようについ聴き入ってしまうような魅力があって、それでもどこか情熱的でもあるところがいい。
遊びもほどよくあって、『European Concert (Live)』に収められている「It don’t mean a thing」なんかは、テンポを倍にして元に戻してみたり、デューク・エリントンの剛気な音遣いにモダンで少し考え込むような思弁的な音遣いを入れてみたり、最後の終わり方もコミカルにしてみたり、単に本質を表現するだけでなく、独自の視点というのが入れられている。
村上春樹が『ダンス・ダンス・ダンス』で女性とベッドに入る前に、作中でこの曲を流した理由は、ムードもあるだろうけど、そういうこととは別に、村上春樹ってセックスする前に、こういうふうにロマンティックなムード作ってるのかもなって素直に思った。
セックスもそうだけど、僕はキスする時の雰囲気って当たり前に大切だと思ってて、個人的にはロマンティックな気分が通じ合ってないのにキスするのは嫌だし、その雰囲気も持ってき方は、恋愛観が出ると思う。
話は逸れるけど、思わず触りたくなるような愛らしさとか、クールさとか、胸があったかくなるような人を迎え入れる包容力を発揮できるかは重要なんだろう。
あのシーンを読むと、お酒飲んで、音楽聴きながら、他愛もないことしゃべって部屋でいい雰囲気になってって流れだから、もしかしたら村上春樹もそういう友達みたいな感覚の恋愛が好きなのかもしれない。
僕が読んだ限りでは、いかにも居酒屋やバーで笑いながらお酒を飲んでしゃべって、部屋に行って、二次会やろっかみたいなノリで、「キスしてみる?」、みたいないかにもそんな感じに見える。
「村上春樹の顔はイケメンじゃない」とか、実はモテなかったんじゃないか」とかいう人がいるけど、僕はモテたと感じる。
そういうこと以前にエッセイに「高校の時の彼女が」とか、そういう話はよく出てくるし、女性ファンも多いのでそれ自体がモテた証拠そのままではあるが。
特に『ダンス・ダンス・ダンス』の冒頭に出てくる僕の彼女は、インテリジェンスを感じさせるキレイそうな女性だし、「月世界の女性と結婚して、月世界の子供を作りなさい」なんて、プラトンの『饗宴』に出てくるディオティマみたいなセリフ、入れるんだもんいい女性に決まってるよなぁとか、僕なんかは思ってしまう。
そんなこんなで相変わらず女性とか、恋愛の話になってしまったけど、こんな話や雰囲気は僕は好きだ。
村上春樹のそんな恋愛が得意そうなロマンティックなところも好きだし、モダンジャズ・カルテットが好きな理由も深くわかる気がする。
了